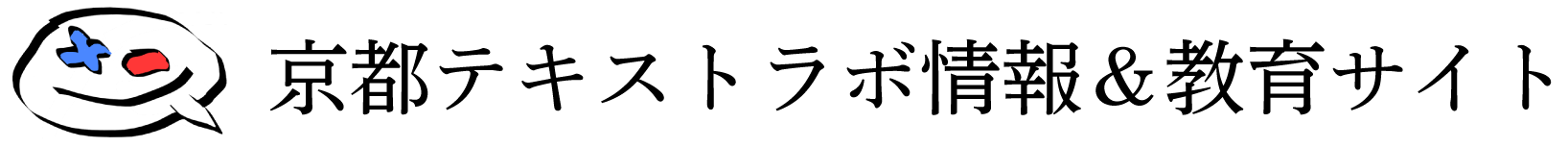ずいぶん間が空いてしまいましたが、文化人類学の研究の結果、わかったことの話です。現地語の植物名はどんなものだったか。
■植物名のゆらぎ
調査村の人たちに植物名や利用法を教えてもらっているときに一つ気づいたことがあります——同じ種類の植物でも、人によってちょっとずつ違う名前を言うことがある——。現地語の植物名は、グループをまとめる名称とそれを細分化する形容部分で成り立っているものが多くありました。日本語でいうと、アカマツ、クロマツのような名前の構成です。ただし、語順は逆ですが。名前の違いは、とくに形容部分でよく生じていました。
ありそうな解釈(仮説)はいくつか考えられます。知り合いの研究者は、村に定住して人々が森林の植物の知識を失いつつある兆候だと言いました(よく知らずに適当に答えるから、答えが一致しない)。他の可能性としては、家族内では知識の共有が頻繁だけれど、家族間ではそれほどでもなければ、親族関係が植物名に影響するかもしれません。
■植物名の分析
植物名のゆらぎの原因を探る前に、植物名の特徴をもう少し説明しておきましょう。主要な果物など重要な植物は、似たような仲間でも一つずつまったく異なる名前があり、総称はない傾向がありました。たとえば、ランブータンの仲間だと、トル、トピリック、ルプ、ムロクット、シャグップ、クマワ、プロシュン、ムーといった具合です。調査村の人たちも似たような植物だと思っていますが、まとめて呼ぶ言葉はありません。
上述の通り、アカマツ、クロマツのようなタイプの呼び分けられ方をしている植物も多くありました。ここで、マツを一次カテゴリー/一次名、アカマツを二次カテゴリー/二次名と呼ぶとします。ひとつの一次カテゴリーに、二次カテゴリーが二つ含まれているのが一番多いパターンでした。でももっと多い場合もあり、たとえば、センダン科の多くの植物をまとめるポルには10以上の二次カテゴリーが含まれていました。ポル・ポティ、ポル・アダン、ポル・ブカカ、ポル・クラブット、……。
さて、この二次カテゴリーの名前の形容部分を分析してみると、よく使われる言葉のタイプがわかってきました。もっとも多く使われていた言葉は、ムン。真のという意味で、日本語でいうと、マアジ(真アジ)の真にあたります。記録した二次名の約7%に使われていました。それから、トコン(山)、パヤ(分水嶺・標高の高い場所)、ブ(川)、ダトゥ(平地)など生育場所を表す言葉もよく使われていました。使われていた16語の合計で、二次名の約1/4で使われていました。色合い、大きさ、毛のあるなしなど植物の形態を表す言葉は27語あり、約1/3で使われていました。
■植物を覚える枠組み
二次名からは、現地の人たちの植物の覚え方が垣間見えるように思います。植物のグループを認識しつつ、形態や生育場所の特徴の違いを覚えていくということです。ただし、二次名は必要がないと言及されないことが多いので、おそらく子どもはある植物を一次名で覚えてから、よく似た別の植物に出会ったときに二つを対比しながら二次名を覚えていくのではないかと思います。私自身の体験ですが、ある日山の中でアカネ科の植物をブコユと教えられました。別の日に別の人に、アカネ科の同属植物ではあるけれども、明らかに別種の川沿いに生えている植物をまたブコユと教えられました。そこで、山にあったブコユと違うんだけど、と私が言うと、それはきっとブコユ・トコン(山ブコユ)でこちらはブコユ・ブ(川ブコユ)、材はブコユ・トコンの方がいいと詳しい説明をしてくれました。
大人たちは二次名も子どもに教えるとは言うのですが、子どもがある程度植物を覚えて、自分から積極的に名前を聞くようにならないと教えようがないんじゃないかなと思います。教えるにしても、何百種類もある植物の二次名をきっちり覚えるまで教え込むというのは現実には難しいでしょう。面白いことに、一人で森に行くようになってから多くの植物を覚えたという人が何人もいました。私の憶測ですが、主要な植物についてはしっかり認識していても、なんとなく知っている植物も多い状態から、一人で森で植物の観察を重ねることによって、ああこれが山〜だなというふうに自分の観察を植物の命名の枠組みに結びつけて整理していくのではないでしょうか。
■植物名の個人差
最後に、植物名のゆらぎの原因に戻りましょう。採集してきた植物を何人もの人に見せて、名前を聞いてみるという調査をしました。子どもや若い女性は明らかに知識が限られていて、名前について人と違う見解を持っているというより、メジャーな植物しか知らない状態でした。若い世代は村で生まれ育っているので、森の植物を知る機会が限られています。子どもにいたっては、二次名の構造だけは知っているものだから、〜バ(森〜)、〜ボカン(焼畑跡〜)と当てずっぽうの答えを言ってみたりしていました。森に住んでいた頃なら、当てずっぽうでも「森」を形容には使わなかったでしょう。すべて森の植物なのですから。
男の子たちは10代半ばになると森で狩猟や換金植物の採集をする機会が増えるので、だんだんと知識が増えていき、30代くらいで一人前の大人といえる知識を持つようになっていました。といっても個人差はあるので、あまり植物を知らない人たちもいました。
そういう調査の中で、植物をよく知っているといえそうな数人に、二次名と植物の対応がどうなっているのか私がとくに気になっていた植物を中心に、名前を聞いてみました。一次名は見事に一致していたものの、二次名の答えはばらばらで、兄弟なら一致する、夫婦なら一致するということもありませんでした。人々が安定して見分けられる範囲を超えて、コミュニケーションに必要とされる範囲を超えて、植物を詳しく見分けて名前で呼び分けようとする文化の力が働いているのかなと思いました。部分的にはやり過ぎ感は否めませんが、その文化的な姿勢が森の多くの植物を高い解像度で認識できる能力につながっているのでしょう。
一連の文化人類学のお話はこれでおしまいです。