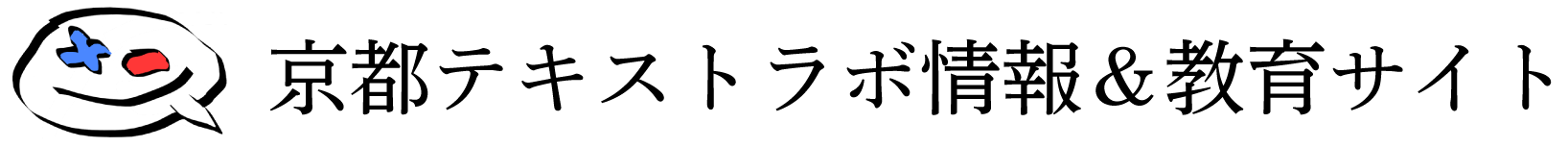シーモア・クレイは「スーパー・コンピューターの父」として知られるコンピューターの設計者である。彼は半田付けのような単純作業から命令セットの設計までこなし、そして仕事に集中できる環境を作るためであれば、一風変わった行動をとるという、天才エンジニアの伝説を体現するような人であった。以下で紹介するエピソードの多くは、チャールズ・マレー(Charles Murray)による“The Supermen: The Story of Seymour Cray and the Technical Wizards Behind the Supercomputer”という書籍によっている。

(National Inventors Hall of Fame)
■生い立ち
クレイは1925年の生まれで、ウィスコンシン州のチペワ・フォールズ(Chippewa Falls)という人口1万人ほどの小さな街で生まれ育った。高校卒業後18才の時に無線技師として第二次世界大戦に従軍し、日本海軍の暗号解読にも従事したということである。彼の経歴を見ると生まれ故郷の地域への愛着があったようで、戦後すぐに結婚した相手は幼馴染、大学はウィスコンシン大学(のちに近隣ながらもより評価の高いミネソタ大学に編入したが)、そしてなによりも、のちに自分が率いることになる会社はチペワ・フォールズに置かれることとなる。
クレイは大学を出るとミネソタ州セント・ポールにある電子機器会社ERAに就職した。ERAは独特な設立経緯を持つ会社であった。アメリカ海軍は戦時中に暗号解読の秘密部門を持っており、そこで計算機を使って暗号解読を行っていた。参加していたメンバーは叩き上げの軍人以外が多かったので、戦後は退役するのだが、その時には暗号解読のノウハウが失われないようにということで、海軍上層部の肝煎りでグループが同じ場所で働いていけるように配慮された結果できた会社であった。そう聞くと会社の風土も堅苦しかったかのように思われるかもしれないが、実際にはその逆で、まさに「自由闊達な工場」という雰囲気の会社だったそうである。
■ERAへの参加
ERAは計算機のノウハウを民生用に展開しようとしていたが、戦争から復員後にして大学を卒業したクレイが地元での就職先を探しており、1950年にERAに参加することとなった。クレイは驚異的な設計・開発の才能を発揮して、数ヶ月後には責任ある職を任され、コンピューターの仕組みについても速やかに学び、2年も経たないうちに、会社の初期主力商品となるERA 1103というコンピューターの設計を任されることとなった。ERAはレミントン・ランドというタイプライター会社の多角化戦略の一環として買収された。レミントン・ランドはUNIVACという有力ブランドを持つコンピューター会社も買収しており、ブランド戦略としてERAが開発した1103はUNIVAC 1103と言う名前で1953年に販売されることとなった。
クレイはその後もUNIVACブランドのコンピューターの設計を続けた。ただ、レミントン・ランドの社風は堅苦しかった。さらには、あのダグラス・マッカーサーを取締役会会長に迎えたため、マッカーサーの戦時中の思い出話を聞くのが取締役の仕事、というような状況であった。ERAのメンバーたちはその企業文化に溶け込めず、機会を見て1957年にコントロール・データ(CDC)という会社を設立した。当初は、海軍との兼ね合いもあって、UNIVACの製品を開発中だったクレイを引き抜くのは憚られたようだが、開発中の製品が一段落したところで、クレイ自身が「だめだと言ってももうこっちに移るからね」といってきてしまった、という逸話がある。

(National Inventors Hall of Fame)
■CDCへの転職
クレイはCDCで新たなコンピューターの開発を担当した。新しい会社で資金繰りに不安がある中、クレイはトランジスター製造会社の品質チェックからこぼれた品質にばらつきのあるトランジスターを集めてきて、それらを組み合わせて安定したコンピューターとする設計を編み出した。他の大卒エンジニアたちの中には「半田付けなどは単純作業担当の労働者にさせればよい」という感覚もある中、クレイは設計と試作品作りの「上から下まで」の工程を自ら行った。
余談だが、筆者も、このように「とにかく全部やる」という姿勢がものづくりでは重要だと思っている。「自分の体を使って部品の性質を感じておく」ということが、他の人にはできない発想につながることがある。クレイはキャリアのほとんどの段階でこの姿勢を持ち続けた。
次回はクレイが設計したCDCのコンピューターについてもう少し紹介していこう。
次回掲載予定は2025年12月上旬頃
著者:大島芳樹
東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。