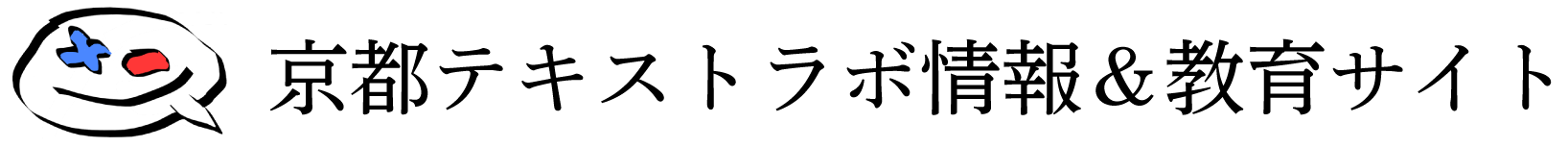文化人類学の研究をしていた頃の話、とうとうメインテーマについてです。そもそも文化人流学の研究を始めたのは、「自然科学を学んでいないけれど、生活の中で自然(たとえば森林)をよく使っているような人たちは、どんなふうに自然を知っているのかな?」という疑問を持ったからです。きっとよく知っているに違いないけれど、自然科学の研究者となにか違いがあるのか、ないのか。
■森林の狩猟採集民が使う植物名を記録する
そんな話を人に相談しているうちに、だんだんと調査民族が決まっていきました(その途中で大学院に入学)。前回少し書いたように、森林の狩猟採集民だった人たちです。「ものすごくよく森の植物を知っている」という知り合いの生態学者の触れ込みで実際に植物を同定している現場を見せてもらうと、さっと植物の種類を見分けて現地語で名前を言っていました。植物の種類を見分けるというのは、植物に対する知識の一部にすぎません。でも、それはどういう植物か、何かに使えるのかといった知識の土台ないしは前提です。たかが名前、されど名前です。
でも、それをどう記録すればよいでしょうか? 単に現地語の植物名を書き取るだけだと、その植物名が何を表しているかわからないので、植物名の語彙の分析しかできません。どの植物を示す言葉なのかもあわせて調べることで、できる分析の幅が広がります。
では、「どの植物」というのはどう記録できるでしょうか? 一番確実なのは、その植物をとっておくことです。実物を残すんですね。だから、調査地にたくさん古新聞を持ち込んで植物標本を作りました。かなり大変な作業ですが、研究の信頼性を高めるという意味でもとても重要な工程です。
話はそれだけでは済みません。実物があるだけでは、他人にとって理解可能なかたちでの分析は実質的に不可能です。研究上の分析のためには、言語化もしくは数値化(記号化)されている必要があります。研究の過程では、しばしば直感が研究を進展させるきっかけになります。でも、直感を直感のままにしておくと、研究にはならないんですね。
研究の世界では、植物の種類を記号化する一般的な方法は学名の使用です。学名は、18世紀にリンネという研究者が体系化した生物の分類と名前の付け方に端を発します。それ以来、名前の付け方のルール(命名規約)がどんどん整備されて、いまでは世界共通の生物名として機能しています。一般の人が学名を聞いても何のことやらわからないという欠点はありつつ、植物を記号化して分析可能にする一つのよい手段です。
■先に熱帯の植物を見る目を養う
さて、調査する人たちとつながりがある生物が文化人類学の研究の射程に入ってきたとき、多くの文化人類学者はその生物の種類を調べるのはその道の専門家に任せます。ところが、私の研究を指導してくれた先生は、「自分で同定せなあかんで」と言うのです。もともと私は生物学を勉強していて、日本の森林で毎木調査(一定の調査区の中にある樹木の種類や太さ、高さなどの調査)をよく手伝ったりしていました。でも、熱帯の植物などまったく知りません。
その先生の勧めで、文化人類学の調査の前に、1か月くらい熱帯の植物を覚える訓練をしました。生態学者の調査ステーションを利用させてもらい、植物採集に同行して植物を実地に観察して、調査ステーションの文献で勉強する繰り返しです。それまで日本の植物をたくさん見てきた経験も役に立ったのでしょう、滞在期間が終わる頃には主要な科を見分けられるようになっていました。熱帯には一つの場所に何百種類もの植物があるので、1種1種をすべて覚えるのはほとんど不可能です。植物同定の第一歩は、科や属といったグループを見分けることです。それができれば頭の中も標本も整理しやすくなりますし、種の同定作業を開始しやすくなります。
植物分類学を少し知っている人に誤解されやすいのですが、文献によく出てくる検索表のように植物を見分けているわけではありません。検索表では、はい・いいえのチャートのように、植物のいろんな部分の特徴を順番に確認していくと種類を特定できるようになっています。これは人に説明するための一つの方法ですが、人の自然な認識をそのまま反映しているわけではありません。実際には(少なくとも私の場合は)、直感的な見分けと論理的な確認的思考の間を行ったり来たりします。あるグループの植物だなと思ったら、そのグループの特徴があるか確認したり、逆にこういう特徴があるグループは何々と何々となどと思い出して、そうか何々だとわかったり。論理的な確認作業でも、順番に分岐していく考え方をしているわけではありません。いろんな特徴を同時に考え合わせます。この見分けに使っている特徴をあえて分岐図に展開すると、検索表になるわけです。
人間は生来備わった能力に基づいて、生物の種類のグループを認識しているとする仮説があります。たしかに、直感的によく似た生き物だと感じたりするので、そうなのかなと思います。同時に、直感的な見分け能力を高めるのに、論理的な確認作業が役立っているとも感じています。いろんな特徴を一つずつじっくり観察する訓練を積むと、直感がより精密になる気がします。ところで、私は観察の着目点を知るのに文献、つまり言語の助けを借りましたが、調査地の人たちが植物を見分ける様子から、必ずしも言語を介在させる必要はなさそうだなと思うようになりました。
■植物の知識を伝授してもらう
少し訓練したとはいえ、私の植物認識能力は調査対象の人たちには及びません。それでも、自分でも植物を見分けられることが調査にとても役立ちました。わかっているから聞ける、理解できるという部分があります。それは他の側面でも同じで、動物に詳しい人なら動物について詳しく聞き取りや観察ができますし、農業に詳しい人なら農業、社会制度に詳しい人なら制度といった具合です。文化人類学ではある社会の全体を観察して理解しようと努めますが、やはり調査者の能力の方向性によって高い解像度で調査できる部分とそうでない部分が出てきます。もちろん能力は伸ばせますから、調査中に興味を持った部分をその社会の中で学びながら調査を進めていくこともできなくはありません。
主題からは逸れますが、調査地の人たちの植物の見分け方で驚いたことがあります。とくに植物をよく知っている人なら植物のどこを見てもその種類をほぼ判別できるのですが、そこまでではない人たちが種類の見分けの手がかりにしているのは樹皮と材だということです。樹皮や材にも植物の特徴が出ているのは認めますが、植物分類学ではどちらかというとマイナーな扱いです。たとえば検索表には樹皮の特徴はあまり出てきません。考えてみると、特徴を言語化しにくいんですね、きっと。図鑑でも色合いや表面の形状(滑らか、縦にひび割れがある、深いひび割れがある、など)はある程度記載されていますが、葉や花や果実の事細かな記載には比ぶべくもありません。とくに花は、形態による分類で重視される部分です(同定は枝や葉からでも可能ですが)。私も自分でも気づかないままに、葉のつき方や形状、花や果実ばかり観察するくせがついていました。付け加えておくと、植物の研究者がみんな樹皮や材を軽視しているわけではありません。材は商業的にも重要ですしね。
閑話休題。調査地の人たちと植物を採集しては、その名前を聞き取り、使い途があればそれを教えてもらい、他にも何か教えてくれればそれも記録して、私はたくさんの植物知識を得ていきました。初めての長期調査の終わり頃、一人のおじさんとその記録にミスがないか確認作業をしました。小学校の先生がインドネシア語をとても上手に教えてくれた話を書きましたが、このおじさんは植物をとてもよく知っているうえに現地の言葉や文化を説明する能力に長けていました。その作業が終わったときに、おじさんがこんな言葉を教えてくれました。“Iyah pekejam akeu’ taman ki’ Lalo”「私を教えてくれたのは私の父ラロである」 本当にその通りで、たくさんのことを教えてもらいました。
■調査結果を分析し、人に伝える
調査によっていろいろなことがわかりました。個別の植物の名前や用途以外にも、調査地のどのくらいの割合の植物に名前をつけているのか、植物をどういうふうにグルーピングしているのか、どのくらい細かく名前を呼び分けているのか、植物の利用性が名前の付け方に影響しているのか、どのくらいの植物をある用途に使えるとしているのか、そういう知識にどの程度個人差があるのか、などなど。
この分析には学名を媒介させていました。種を分析単位に使い(例:調査で採集した何種の植物のうちで、名前がなかったのは何種類か)、植物の類縁関係の参照元にしたのです(例:センダン科の植物を総称する名前がある)。断っておくと、種や科などの分類は絶対的なものではなく、作業仮説的なもの、便宜的な呼び名的なものです。ゆるぎないものとして種を捉えている生物学者など現代ではほとんどあり得ません。種をグルーピングする属や科などは、研究の進展に従って頻繁に修正されるうえに、塩基配列から解明できる類縁関係をすべて反映できるわけでもありません。ただ、学名は厳密に命名の元となった標本(タイプ標本といいます)と結びつけられています。言葉だけが一人歩きしない仕組みがあるのはよいところかなと思います。
さて、学名を使いながら分析結果を大学院のセミナーで発表すると、専門性が近い文化人類学の先生方の大不評を買いました。西洋分類を基準にするのはおかしい、と。植物分類学はヨーロッパのキリスト教の信仰心から生まれたとはいえ、現在においては世界中で行われている研究の集合体だと私は理解していたのですが。しかも、西洋ないしは科学的な分類をより優れたものとして参照していたのではありません。名前の対象となっている植物が何かを示すのが主目的です。植物標本をセミナーの場に持ち込んで示すのは、現実的ではありません。それができたところで、植物を見る目が養われていない人にとっては、無味乾燥な標本をどう理解していいかわからないでしょう。記号化されているからこそ、知らない人でも論理的に取り扱える、理解できる対象になるのです。
それは誤解だと説明しましたが、最後まで誤解は解けなかった気がします。あるいは、私は本当に西洋ないしは現代科学至上主義に立っているのでしょうか。そうだとしたら、ものすごい時間と労力をかけて、カリマンタンの山奥で調査するモチベーションはなんだったのでしょうか。論文の査読ではこの批判は受けなかったので、基本的な分析の方法論は変えずに結果を発表しました。それでよかったんじゃないかと思います。
次回は植物の名前について具体的な話を書こうと思います。