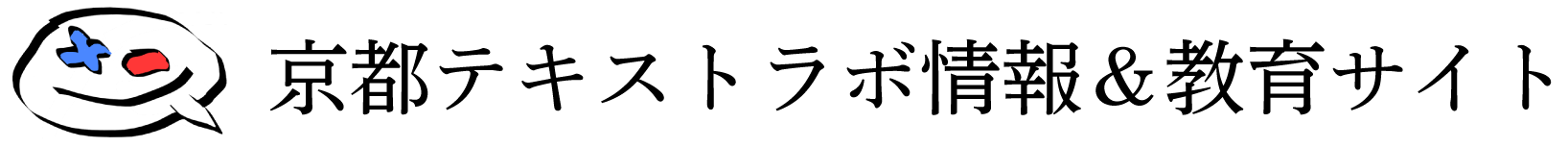この連載の第8回と第9回でJ. C. R. リックライダーを取り上げた。リックライダーはマサチューセッツ工科大学(MIT)の社会学部・心理学科で学者としての活動をはじめたものの、研究内容が斬新だったために学部上層部に睨まれてしまった。それによって新規大学院生の採用ができなくなり、アカデミックでの成功、つまり論文を発表し学生を育て、分野を発展させるという道を絶たれてしまった。そのため、彼は1957年に心理学研究を離れ、BBNという会社の副社長として迎えられることとなった。BBNはもともとMITで音響工学を研究していた教授たちが(“BBN”は創立者たちの名前の頭文字である)、映画館や劇場の音響設計をする会社として始めたものである。ただ、MITとの深いつながりを保っていた。

詳しくは下の「PDPの登場」参照
■コンピューターへの情熱
リックライダーはBBNに入った頃にはすでにリンカーン研究所での活動でコンピューターへの強い情熱を持っており、音響の会社だったはずのBBNで「BBNもコンピューター事業に進出しなくてはならない」と主張して、自分で使えるコンピューターを調達することに成功した。BBNに一番最初に導入されたのは、LGP-30という現在では忘れ去られたコンピューターであり、管理が面倒な真空管を使ったものであったが、それでもリックライダーは手元に自分で使えるコンピューターを持つこととなったのである。
リックライダーには、才能のある人間を魅了して自分のグループに呼び寄せる独特な才能があったようで、リックライダーに触発されてBBNにもコンピューター関係の人材が集積されていくこととなった。
■PDPの登場
同時期に、リンカーン研究所でTX-0の開発を主導したケン・オルセン(Ken Olsen)は、ハッカーたちがTX-0に取り憑かれる様子を目撃し、TX-0に類するような比較的「小型」のコンピューターを製造・販売するビジネスが成り立つとになると踏んだ。彼は仲間とデジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)という会社を興し、TX-0に近いアーキテクチャーを持ったコンピューターの設計を始めた。このコンピューターは“Programmed Data Processor”(PDP)と呼ばれたが、“Computer”という言葉が入っていないのは政治的理由だそうである。最初のモデルのPDP-1から始まる一連のコンピューターは、コンピューティング史に名を残すこととなったので、この連載でものちに何度も名前が出てくることになるだろう。

■“小型”コンピューターとの対話
BBNとDECはメンバーたちがもともとリンカーン研究所つながりだったこともあり、また優秀な人材がいることから、DEC PDP-1の試作機(製造番号0番)をBBNに設置し試用してもらうこととなった。写真にあるように、現在の基準からはかなり大型のコンピューターのようにも思えるが、当時はこれは小型のコンピューターだったわけだ。リックライダーは、これ以上楽しいものはない、という感じでこれを使い倒した。この連載で何度も述べているように、対話的に使えるコンピューターには独特の「魔力」があり、頭の中にあるアイディアをコンピューターにぶつけ、それが思った通りであるかどうかが即座にわかることによってアイディアを改良していく、というフィードバック・サイクルを生み出すことができる。MITのハッカーたちは時間を決めて交代でTX-0を使っていたわけだが、リックライダーは、ごく少数の優秀な同僚と一緒に、自分だけのコンピューターを使えるようになったことになる。本人の回想によれば、この頃はとにかく書いたプログラムが実行できるのが楽しく、別に書いたものを保存しようとさえ思わなかった、と言っている。
■人とコンピューターの共生関係
リンカーン研究所に始まるコンピューター体験といろいろな人々からの影響を受けて、リックライダーは人間とコンピューターの関係について深く考えることとなった。普通の機械であれば人間はそれを道具として使うだけだが、コンピューターは人間に「使われる」だけではない双方向的な関係になりうるものである、という発想が育まれることとなった。ここでは、人工知能のように機械だけが自力で考えるようになる、というような簡単な話でもなく、イチジクの実の中に住み花粉の受け渡しをする代わりに栄養をもらうハチのように、人間とコンピューターが「共生関係(symbiosis)」になりうる、というアナロジーが使われていた。リックライダーはこの視点を、研究の方向性を示すことを目的とした論文「Man-Computer Symbiosis」としてまとめ、それを1960年に発表した。この論文は、のちのコンピューターやネットワークの設計に携わる多くの人に影響を与え、リックライダーの人脈と活動範囲をまた広げるきっかけとなっていった。
次回は、この頃のリックライダーについて、京都大学の喜多千草先生による『インターネットの思想史』からの記述も交えて紹介していきたい。
次回掲載予定は2025年1月上旬頃→1月3日に公開しました(こちら)
著者:大島芳樹
東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。