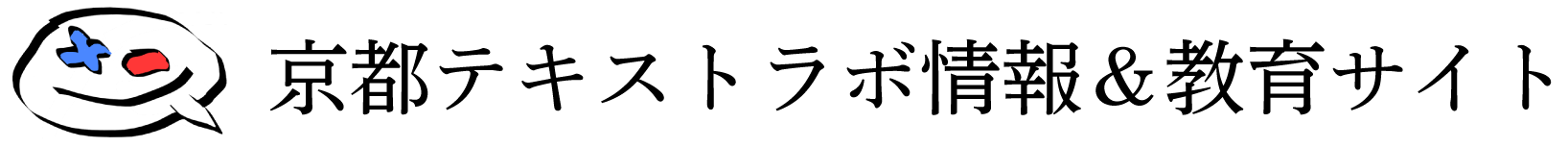前回に引き続き、ハッカー文化と呼ばれる、学術的研究ではない方向からコンピューティングの歴史を動かした流れについて触れていこう。
■プラクティカル・ジョーク
マサチュッーセッツ工科大学(MIT)に来るような学生の中には、「世界に新たな知をもたらすためなのだ」という建前から、他人が決めたルールなど気にせずに自分の好奇心のままに行動する傾向を持った者がいる。この傾向は、「みんながびっくりするようなプラクティカル・ジョーク」を仕掛けてみたいという欲として現れることもある。彼らは生半可でない頭脳と技術を持っていたので、「どっきり」をしかけたいと思えば、それを達成する能力が十分にあったわけである。そのため、MIT近辺では時々例えば建物の屋根に車が持ち上げられて載っている、という類の手の込んだいたずらが行われていた。ひらめきを「工夫」で形にすることは、「てっとりばやく斧でひっぱたいて組み合わせてしまう」というアナロジーから「ハック(hack)」と呼ばれていた。

■ハッカー文化の芽生え
鉄道模型クラブの「信号と動力(Signals and Power: S&P)」のメンバーにとっては、コンピューターとは知的好奇心を刺激する夢の機械であり、それを使って「皆が驚くようなことをする」のは、まさに「ハック」と呼ぶに相応しい活動だったわけである。このグループからは、学業などそっちのけでコンピューターいじりに没頭する者が多数出てきた。彼らにとっては、ただ純粋にプログラムが「書けるやつ」であるか、そして同じ結果を出すプログラムでも、1命令でも削って「完璧・究極のプログラム」を目指す才能と根性があるのか、ということのみが、グループ内での尊敬を勝ち得る基準として重要となったのである。知の集積を最大限に効率化するために、知識・情報とはとにかく皆で共有するべきである、そしてコンピューターとプログラミングは自分たちのアイディアによって思いのままにしていくことができる、という発想のもと育まれていったのが「ハッカー文化」である。
プログラミングにはそのような極端性と根性が必要であることは間違いないのだが、その環境にいた人の中には、人物を『できる人』か「できない人」の一つの軸だけでバッサリと切り分けてしまい、できないと見なされた人には遠慮なくキツく当たる、という側面に傷ついていた人もいた。例えば、筆者と交流のあるブライアン・ハービー(Brian Harvey)は『ハッカーズ』にも登場する人物である。ハービーは、ハッカー文化の中で育ち、のちのキャリアの中でその文化を勤務地に「移植」したようなハッカーであるが、プログラムの設計方針で意見の食い違いがある時に「できない人」という態度を取られるのがいやだったと言っていた。
■対話性の魅力
それはともかく、この連載でも何度か触れたように、コンピューターが持つ魅力の一端は、自分の行った動作とコンピューターとの反応が短いフィードバックループで繋がれており、何かすればすぐに反応がある、そして正しく打てば正しく響くという「対話性」にある。
1959年ごろまでは、MITに導入されたのはIBM製のバッチ処理をする機械であった。第13回で紹介したビデオの前半にあったように、紙の上で「デバッグ」し、パンチカードを打ち出す機械を使ってパンチカードの束を作り、それをオペレーターに渡す。オペレーターは建物の別の階にあったりするコンピューターに空き時間が来るのを待ってプログラムを走らせ、何時間後かに結果をユーザーに渡す。オペレーターにとってはコンピューターを守るのが仕事ではあるが、学生たちにとってはオペレーターがコンピューターという魔法の機械を独り占めしているように見えたわけだ。鉄道模型の信号機に魅力を感じていた学生たちは、とにかく「自分で扱って、その結果をすぐみたい」と夢想したのであった。
ハッカーたちにとって、余剰品として回ってきたTX-0はそれまでのコンピューターとは違い、自分自身で機械の前に座って操作し、その実行の様子を見ることができ、さらには実行している部分に応じて音を出したりすることができる夢の機械だった。
次回掲載予定は2024年11月上旬頃
著者:大島芳樹
東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。