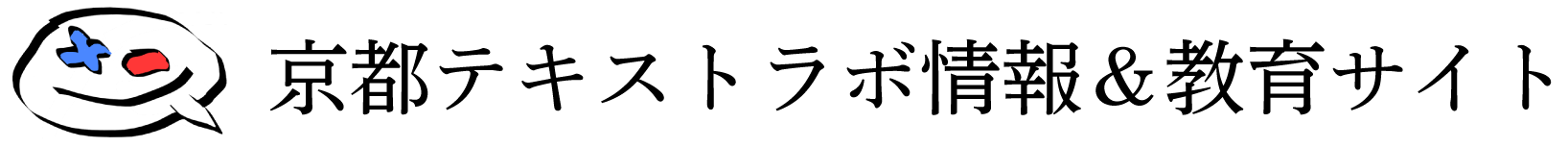文化人類学で言葉に関係した内容を投稿していきます、と書いたばかりですが、今回は一瞬言葉が追いつかない感覚について書いてみたいと思います。
目次
■味
インドネシアで長期調査を始めて3か月くらい経ったときのことです。調査に必要な物品を調達するために、カリマンタンの山奥の村と河口の町を往復しました。今回の話題とは直接関係ないのですが、移動手段は大きな長いボートです。商人が化石燃料、衣料品、雑貨、食品などを運搬するためのボートが長距離交通の役割も担っていました。ボートの旅でまっさきに思い出すのは心地よい風を受けながら川面を進む情景ですが、屋根も何もないので、強い日差しに耐えたり、雨に耐えたりの旅でもありました。風もずっと当たり続けると辛くなってきますしね。下りは早朝に上流の大きな村を出発して夕方に河口の町に着きますが、上りは川を遡るうえに船荷も重いので川辺の空き小屋で一泊することがよくありました。
さて、話を戻して、物品調達のついでに下流の村にも滞在しました。村の小学校の先生家族の奥さんの親類のところに遊びにいかせてもらったのです。そのときに、みんなでkepurung(クプルン)という料理を一緒に作って食べました。ネットで調べてみると、kapurung(カプルン)というのが正しい名前かもしれません。わらび餅のようなプルプルしたものと野菜などの具をピーナツベースのスープに入れて食べるものです。地元の料理ではなく、ブギスの人から教えてもらった料理だと言っていました。ブギスというのはスラウェシの民族で、大工仕事が上手な人が多いらしく大工としてカリマンタンに出稼ぎに来ている人、そのままカリマンタンに残っている人がよくいました。
料理が出来上がって、一口食べた瞬間、衝撃が走りました。なに、この味?? しばらく考えて、やっと理解が追いついてきました。ピーナツベースのスープという馴染みのない味の中に、予想していなかった懐かしい味があったのです。懐かしい味の元は、なんと缶詰のイワシ。カリマンタンの山奥で生活している間、魚はずっと川魚でした。川魚にもいろいろな種類がありますが、どれも海のものとは違う匂いをもっています。それまで日本食を思い出すことはまったくなかったのですが、味覚なのか嗅覚なのかと繋がっている感情がイワシに強く反応したのですね。
■気温
約1年の調査を終えて、関空に飛行機が着いて、荷物を受け取り、JRの駅に向かってターミナルビルを出たときです。いままで経験したことのない、言葉にならない感覚に体が衝撃を受けました。……単に寒かったのです。「いままで経験したことのない」というのは本当ではなく、体も頭も忘れてしまっていただけでした。
インドネシアは温暖で、「暑い」から日本語でいうところの「肌寒い」程度の気温の幅で1年を過ごしました。肌寒い程度で、dingin(寒い)なんて言っていました。それが、その日(12月10日)の関空付近の気温は摂氏0度。自分の中の「暑い〜寒い」の幅からまったく外れた寒さだったんですね。
■言葉にするということ
いまでは外国に行っても、帰国しても、言葉にならないような衝撃を受けることはなくなりました。それはつまり、たいていの感覚を瞬時に位置づけることができるようになったということなのでしょう。経験を積んだということかもしれません。
感覚の位置づけに言葉は必要不可欠というわけではありませんが、自分の中の感覚を位置づけることと言葉を使うことは深い関係があるように思います。ある感覚を特定しているからこそ、そこに言葉が与えられます。逆に、言葉を使って考えることで、その感覚を分析することもできます。
自分が子どもだった頃のことはよく覚えていませんが、子どもは言葉より先にくる感覚にたくさん出会いながら成長しているんだろうなと思います。
若者はいろいろな「もやもや」を抱えがちですが、これも言葉になっていない状態なのかなと思います。五感から来るものではなくて、もう少し複雑な感情——自分のこと、他者と自分との関係、社会と自分との関係から出てくる感情——から来る感覚です。「もやもや」を抱え続けるのが辛くなってしまったら、それを言葉にしてみるといいかもしれません。書くのでも、独り言でも、誰かに話すのでもよいので、思いつくままに書いているうちに、話しているうちに、いつしか形が現れてくると思うのです。形ができれば(位置づけられれば)、どうすればいいのか考える糸口になるでしょう。
また、最後に強引な展開で話を締めてしまいましたが、次回はこういう情緒的な話ではなくて、客観的な文章を書くことについて書いてみたいと思います。