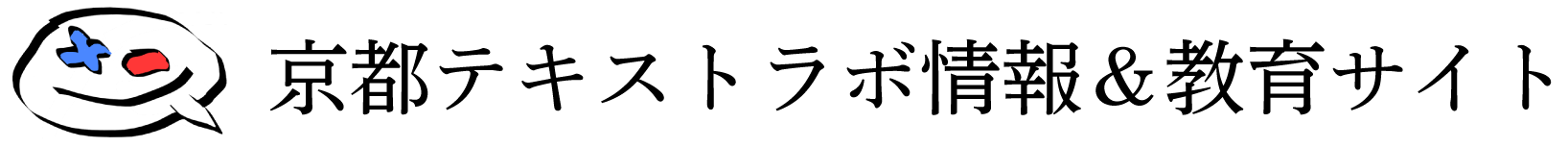今回はダグラス・エンゲルバートについて紹介しよう。エンゲルバートがコンピューティングに興味を持っていくエピソードは、ハワード・ラインゴールド(Howard Rheingold)が『Tools for Thought』という本を書くためにエンゲルバートを取材した内容を参考にしている。ちなみに、ウォルドロップによる『The Dream Machines』でもこのあたりのエピソードは『Tools for Thought』からの引用として紹介されている。
■きっかけ—As we may think—
エンゲルバートは1925年生まれである。大学で電気工学を学んでいたところ、在学中に米国海軍に徴兵され、レーダー技師として第二次世界大戦に従軍することとなった。終戦後は大学に戻り、数年遅れながら電気工学の学士号を取得して職についた。ただ、戦時中に読んだ“As we may think”という雑誌記事に書かれていた将来のコンピューター像が、頭の中にずっと引っかかっていた。
仕事はNASAの前身となる「アメリカ航空諮問委員会(NACA)」で設備整備技師という安定した職で、ほどなく結婚もした。本人の回想によれば、通勤で車を運転している時に「もしかして人生のゴールをすでに全部達成してしまったのでは」という感覚に襲われたそうである。ただ、朝鮮戦争や冷戦が続く社会情勢を見て、現代社会が直面している問題は技術の進歩とともに大きくなっていくばかりであり、それらの問題を解決する方法も作っていく必要があると感じるようになった。いわば、「世界を救うことを新たな人生の目標にしよう」と考えたのである。“As we may think”が語っていたコンピューターを使った知的活動をもとに、「人間の知性を拡大すること」を問題解決の糸口として提供する、という構想となった。
■コンピューターに関する研究の道へ
この目標に進むために、退職してカリフォルニア大学バークリー校でコンピューターに関する研究で1955年に博士号をとった。ただ、博士号の内容はプラズマ現象を使って論理素子を作るという、エンゲルバートの名を高めた「知性の拡張」というビジョンと比べると「地に足のついた進歩」ではあった。インタビューによれば、大学院で「知性の拡張に関する研究をしたい」と言っても、周りからは「そんな夢物語をしていないで、ちゃんとした研究をしろ」という反応をされたそうである。
■「知性の拡張」の研究構想
博士号取得後も論理素子レベルの研究を続けてはいたものの、「知性の拡張」の研究をする機会を探しており、1957年にスタンフォード研究所(Stanford Research Institute:SRI)というシンクタンクでの研究職に転職した。SRIでも当初は磁気論理素子などの研究をしたが、上層部の説得に成功し、「知性の拡張」に真っ向から取り組む研究の構想を1962年に“Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework”という文書にまとめた。彼のいう知性の拡張は、「コンピューターを使えば仕事が便利になる」というようなレベルに止まる話ではなく、「道具(artifact)とは何か」、「言語と記号、概念との関連はどうなっているのか」、「教育(training)と道具との関係とは」、「それらを組織化する方法論とは」という高い次元からのアイディアを出発点とし、「動的に変換する記号を操作することによってどのような作業が可能となるか」という構想に展開していくものである。もう一つ言えば、参加している人間を含め関与している要素を入力と出力があって内部状態が変化するような「プロセス」として捉え、コンピューターを使ってそれらをどのように効率よく組織化することができるのかについて追求する、という方向性であった。
“A Conceptual Framework”の前半はそのような大所高所の話が多く、その中でも、「道具が思考を規定するのか?」という議論をする時に「では、レンガのような形をした鉛筆を使って字を書こうとしたらどうなるだろうか」と言って、実際にその実験をした結果が載っていたりもする。
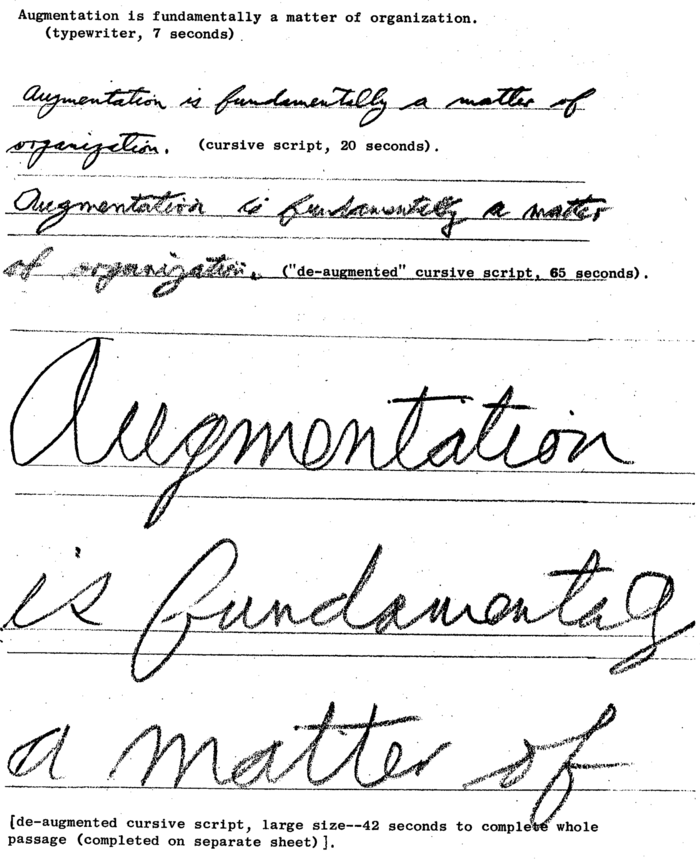
文書の後半はそのようなコンピューター・システムを使う人物たちの振る舞いを描いた「読み物」風になっている。
エンゲルバートはARPA IPTOからの助成も受け、開発チームを組織して彼の理想となるコンピュータ・システムを実際に作り出すことに邁進する。その後は彼のグループで作っているシステムを日常的に使用しつつ、改良をし、稿を改めて紹介することとなる有名な1968年の発表会につながったわけである。
次回掲載予定は2025年6月上旬頃→6月2日に公開しました(こちら)
著者:大島芳樹
東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。